青魚、と聞くと、どこか庶民的な響きがする。栄養価が高く、脂がのり、そして安価。だがその中にあって、唯一無二の存在感を放ち、「青魚のブルゴーニュ」とでも言うべき風格を湛える魚がいる。それが、「関サバ」だ。

関サバとは何者か?
関サバとは、豊後水道に面する大分県佐賀関(さがのせき)で一本釣りされたマサバのうち、一定の品質基準を満たしたものにのみ与えられる“称号”である。言うまでもなく「サバ」は日本の食卓に古くから馴染みのある魚だが、関サバはその中でもまさに選ばれしエリート。通常のマサバとは、育ちも、味わいも、管理方法すらも異なる。
ここで重要なのは「関」という地名と、そこに広がる豊後水道の地形的特性だ。急峻な海底地形と潮流の複雑な交錯が、関サバの肉質に決定的な違いをもたらす。要するに、天然の“水中ジム”で育ったようなもので、身が引き締まり、脂と旨味が絶妙なバランスで共存している。

一本釣りという矜持
関サバは乱獲を避けるため、また魚体へのダメージを最小限に抑えるために「一本釣り」が義務付けられている。網での漁獲とは異なり、魚が他の個体とぶつかることなく、水揚げ後もストレスを最小限に保ったまま活け締めされる。この工程が、血合いの美しさや臭みのなさ、さらには刺身で食べられる鮮度の維持に寄与している。
通常のマサバであれば、生食は避けられるべきだ。サバ特有のアニサキスや鮮度落ちの早さが理由である。しかし、関サバはそのリスクを徹底した管理と短時間での流通によって回避している。まさに“生で食べるために存在するサバ”なのである。

見た目の違い──鑑定眼を持つ者のみが知る美学
プロの目は、関サバをひと目で見抜く。魚体はふっくらと太り、体表は銀色というよりも、やや青みを帯びたメタリックな光沢を放つ。鱗のひとつひとつがまるで七宝焼きのように繊細な光を返し、いわば「和の装飾品」のような佇まいすらある。
さらに目を引くのが、腹部の硬さと弾力。これは、脂がただ多いだけでなく、筋肉繊維との絶妙なバランスが保たれている証左である。脂が勝ちすぎてベチャッとするようでは、関サバとは呼べない。

味の構造──複雑にして端正
刺身にして口に運んだ瞬間、まず舌を包み込むのは甘味に似た脂のまろやかさ。次いで遅れてやってくる旨味の濃度。それはまるで、グルタミン酸とイノシン酸が密かに会合を開き、調和を図った末に送り出してきた“旨味の合奏”とでも言うべきものだ。
そして特筆すべきは“後味の潔さ”である。脂が濃厚でありながら、口中に残るのはむしろ清涼感に近いもの。この感覚は、鰯や秋刀魚では決して味わえない。青魚でありながら白身のような透明感すら感じるのは、まさに関サバ特有の個性といえよう。
ブランド化の功罪
1980年代後半、関サバはその味と品質管理の徹底から、全国的に知られる“高級魚”の地位を確立した。しかし、ブランド化とは諸刃の剣でもある。模倣や“なんちゃって関サバ”の出現、価格のインフレ化、それに伴う地元漁師のプレッシャー──そのすべてが関サバを取り巻く現実でもある。
それでもなお、関サバはブランド魚の枠を超えた存在だ。なぜなら、関サバは単なる「商品」ではなく、「海と人と技術の結晶体」だからである。
関サバを味わうという体験
最後に、関サバを味わうとはどういうことか。これは、単なる“食事”ではない。そこには海流の力学、漁師の技術、流通のスピード、そして料理人の目利きと包丁さばき──すべてが見えないレイヤーとして積層している。
一切れの刺身に、これほどの背景と物語が込められている魚は他にそう多くない。関サバとは、そうした複層的な「食の文化」を体感させてくれる稀有な存在なのである。


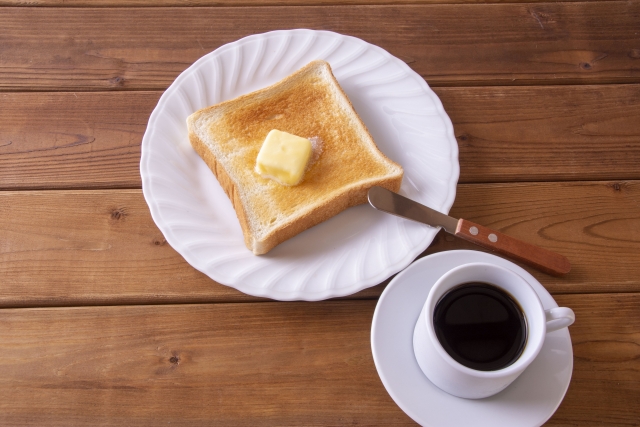

コメント